国家サイバー統括室が発足:中小企業こそ「防衛の最前線」に立つ時代へ

国家サイバー統括室の発足という大きな転換点
2025年7月1日、内閣官房に「国家サイバー統括室(NCO)」が新たに設置されました。「国家サイバー統括室」は、現内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)を改組し、およそ240名体制で運営される組織です。サイバー空間における脅威は、今や国家の安全保障や経済活動に深刻な影響を及ぼす現実的なリスクとして認識されており、その対応は急務とされています。。

この統括室の発足は、すでに成立している「能動的サイバー防御(ACD)」関連法案と連動した動きであり、単なる組織強化にとどまらず、実効性あるサイバー防衛の中枢機能を担うことが期待されています。自衛隊や警察との連携もさらに強化され、いわゆる「宇サ電(宇宙・サイバー・電磁波)」という新たな戦略領域において、官民一体となった防衛体制が動き出そうとしています

こうした動きは一見、大企業や政府機関だけに関係する話のように思われがちですが、実際には中堅・中小企業もサイバー空間における重要なプレーヤーであり、時には攻撃の標的や踏み台として利用されるリスクを抱えています。「国の話だから自社には関係ない」という認識は、もはや通用しない時代になったと言えるでしょう。
本記事では、国家レベルのサイバー対策が今どのように進化しているのか、そしてそれが中小企業にとって何を意味するのかを解説しながら、今後中小企業に求められる実務対応について考えていきます。
誤解されやすい「国家の話」だという距離感
「国家サイバー統括室の発足」や「能動的サイバー防御」といった言葉を耳にすると、政府機関や大企業を対象とした話であり、自社には関係ないと感じてしまう方もいるかもしれません。しかしそれは大きな誤解です。
実際のサイバー攻撃は、防御が甘いとされる中小企業を足がかりにして進行するケースが非常に多くあります。特に攻撃者は、ボットネットの構築を目的に、セキュリティ設定が不十分なWi-FiルーターやIoT機器(家庭用も含む)を狙います。これらの機器は初期パスワードのまま使用されていることも多く、購入直後から「ボット化」のリスクを抱えていることも少なくありません。これらの機器が乗っ取られれば、企業は知らぬ間に攻撃の「中継拠点」となってしまう可能性があります。
また、現代ではテレワークが一般化し、従業員の家庭用ネットワークと企業の業務システムが密接につながっていることも珍しくありません。そのため、家庭のネットワークが攻撃を受けた場合、そこを経由して社内ネットワークにマルウェアが侵入するリスクも現実的です。特にサプライチェーンの一角を担う企業は、攻撃者にとっての「本命(政府機関や大企業)」に至るための入り口として悪用される可能性が高く、自らが直接的な標的でなくとも深刻な影響を受けるおそれがあります。本命である「政府機関」や「大企業」を直接狙う戦略も否定はできないものの、中小企業が主要ターゲットになりやすいことを忘れてはいけません。
国がサイバー空間を国家安全保障の重要な戦略領域と位置づける今、企業規模問わず全ての組織がその防衛の一端を担っている、という意識を持つことが求められるようになったということです。
国の対策強化=企業への期待と責任の増大
国がサイバー攻撃元に対する能動的な対応を強化する中で、民間企業にも「早期の脅威発見」や「通報体制の整備」「日常的なセキュリティ対策の徹底」といった主体的な取り組みが、これまで以上に求められるようになっています。今後は、国家サイバー統括室によって法制度や各種ガイドラインの見直しが進み、企業に対してより具体的な対策指針や対応要件が示されていくと予想されます。特に中小企業に対しては、情報共有の体制構築や、必要に応じた通信状況の把握・分析といった協力体制の構築が求められる可能性もあります。
政府主導による対策の強化は、企業にとって「ただ守ってもらえるだけ」の話ではなく、責任や制約も伴います。たとえばランサムウェアの被害を受けた際、犯人に身代金を支払えばすぐに復旧できる、と安易に考える企業もありますが、これは極めて危険な判断です。米国では、OFAC(外国資産管理局)の規制により、テロ組織や国家支援型のサイバー攻撃者など「制裁対象」とされた相手に対して金銭を送ることは、たとえ身代金であっても違法行為に該当する可能性があります。実際に、ランサムウェア攻撃者の中には北朝鮮系やロシア系など、制裁対象とされているグループが多数存在しており、知らずに送金することで企業が法的責任を問われるケースも出てきています。
そしてこのような規制は、今後日本国内でも導入・議論が進む可能性があります。たとえば、身代金の支払いを事後的に届け出る義務や、支払い自体を制限する法律が整備されることも十分に考えられます。こうした動きが進めば、「身代金を払って復旧させる」という選択肢はますます許されなくなり、代わりに「被害を防ぐ体制づくり」が企業に強く求められるようになります。
特に中小企業にとっては、万が一の被害で多額の身代金や損失を支払うことになれば、キャッシュフローが止まり、事業継続自体が危うくなるリスクもあります。そのため、今後は単に対策を取るだけでなく、「対策を取らなかった場合のリスク」まで見据えたセキュリティ戦略が必要不可欠です。
さらに、ベンチャー企業や中小企業にとっては、サイバーセキュリティ対策評価制度(例:独立行政法人が示すセキュリティ☆ランクなど)によって、取引先企業からの信用評価や調達可否に直結する事例も想定されます。サイバーセキュリティは単なるITの問題ではなく、「取引条件」や「資金調達の可否」といった経営判断に影響を与える要素となっているのです。

中小企業が持つべき心構えと今後の実務アクション
では、これから中小企業はどのような心構えでサイバーセキュリティに向き合うべきなのでしょうか。国家サイバー統括室の設立によって対策の方向性が急激に変わるわけではありませんが、今後は国による規制強化や対策フレームの整備が進み、企業にもより具体的な対応が求められるようになると考えられます。
中でも注目されるのが、サイバーセキュリティ対策評価制度」に代表される可視化の枠組みです。これらの制度には法的な強制力こそまだありませんが、自社のセキュリティ水準を客観的に見える化し、段階的に改善していくうえで、非常に有効な指標とります。今後の取引継続や外部からの信用評価においても、大きな意味を持つでしょう。
セキュリティに関する制度やガイドラインに対しては、「対応が煩雑」「人手が足りない」といったネガティブな印象を抱かれることも少なくありません。しかし裏を返せば、国が一定の方向性や評価軸を示してくれている今は、何の指針もなく場当たり的に対策を進めていた頃に比べ、むしろ効率的に整備を進めるチャンスとも言えます。
まず優先すべきは、「自社のセキュリティ課題を正しく可視化すること」です。現状の対策レベルや潜在的リスクを把握しなければ、効果的な改善は始まりません。可視化を行う際には、国や業界団体が示す評価指標や格付け制度を参考に、段階的な見直しを行うことが非常に有効です。

一方、セキュリティ対策というと、EDRやNGAVなどの高度なツールの導入が必要だという認識を持たれがちですが、実際にはガバナンス・コンプライアンス・リスク管理(GCR)といった「統制」に関わる取り組みが、対策全体の土台を支えています。すべての対策にコストをかける必要はなく、自社に合った優先順位とバランスが重要です。

また、企業規模や人員の制約から、自社で高度なセキュリティ体制を構築することが難しい場合には、IaaSやSaaSといったクラウド基盤の活用も現実的な選択肢です。外部のセキュアなプラットフォームを活用することで、自社の責任範囲を適切に限定しつつ、高いレベルの保護を享受できます。メールやファイル管理、ウイルス対策などをクラウド上で運用すれば、脆弱性対応や障害監視などの技術的負荷は提供事業者が担うこととなり、自社は設定やアクセス管理など運用面に集中できます。先日の株式会社大創産業による Google グループ漏えい事件からも分かる通り、決して「権限周り」の管理は疎かにしてはいけません。

このように、「すべてを自社で守る」という発想から脱却し、「どこを委ね、どこを守るか」を整理する“責任分担”の視点こそが、これからの中小企業にとって持続可能なセキュリティ戦略となるのです。
- 「国家の話だから関係ない」という考え方は危険
- 国家の動きは、民間企業への期待と責任の増大につながる
- 身代金の支払いが違法となるリスクもある
- 国の方針に沿って、自社の対策レベルを可視化することが重要
- すべてを自社で守るのではなく、「何を委ね、何を守るか」を明確に
- まずは「現状把握」と「課題の可視化」から
なお、サイバーセキュリティラボでは、「サイバーセキュリティ対策評価制度への対応」や「中小企業でも実践可能なセキュリティ可視化・改善策」に関するセミナーや解説記事を順次公開していきます。制度の動向や実務面での疑問をお持ちの方にとって、有益な情報発信を行ってまいりますので、ぜひ今後のご案内にもご注目ください。
2026年度のサイバーセキュリティ評価制度開始に向けた具体的な対策について解説した収録セミナー動画はこちら↓
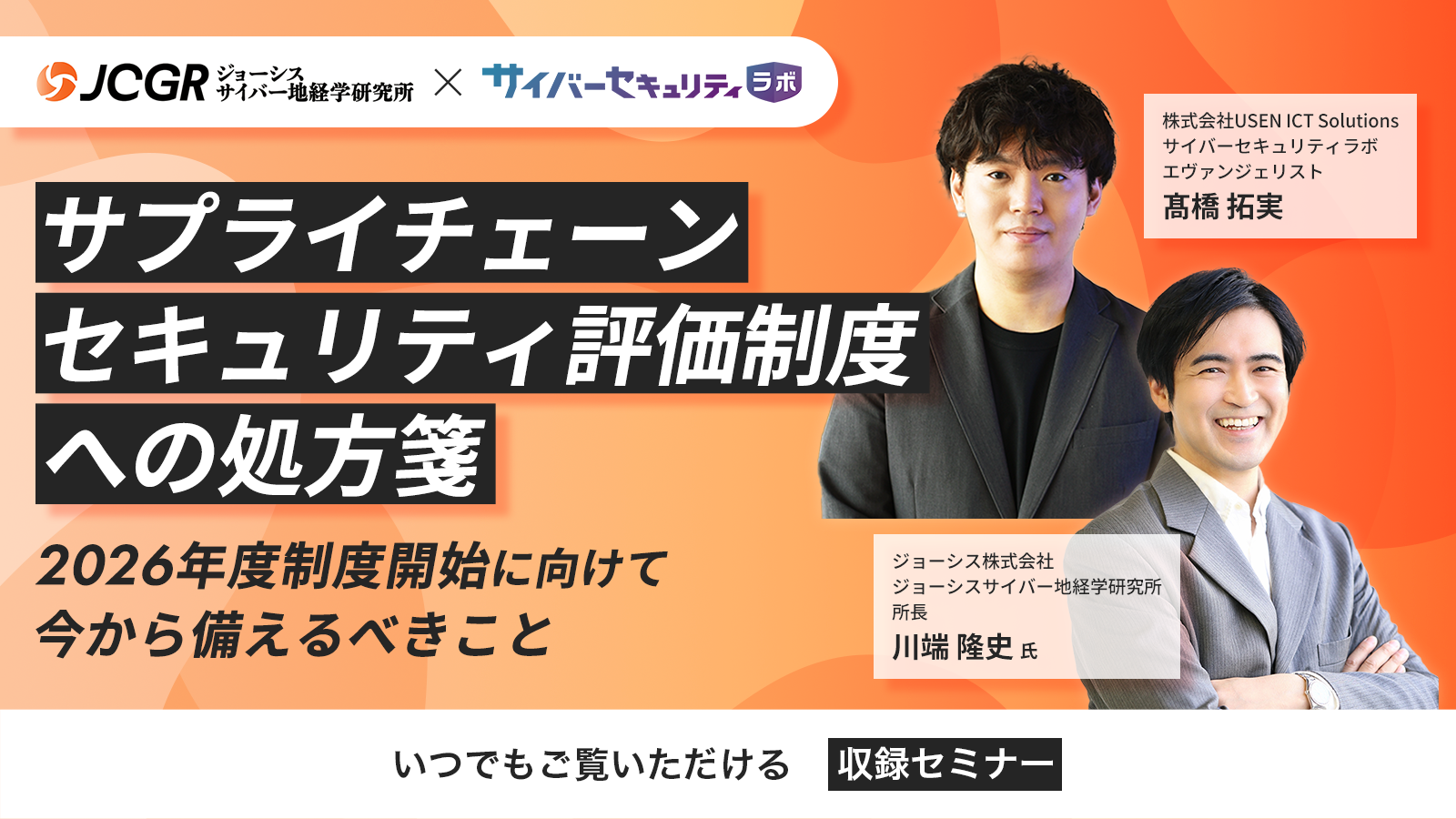
※収録型のWebセミナーなので、お好きなときに視聴いただけます。
執筆者
